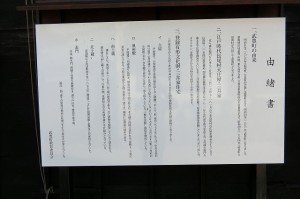弓道について
北斎漫画と源頼政の鵺退治図である。
アーチェリーもそうだけれども、「的をねらう」場合は、このような形になる。当然である。
弓道家がこれを見ると「北斎の勘違い」ということを言い出すのだけれど、「動く的をねらって射る」場合はこれが正しい。
ポイントは、右ひじが矢とまっすぐになるところで、このひじと弓手で「ねらいを定める」。
葛飾北斎という男の観察眼は並みのものではない。手首足首が人の表情として絵に表れることを知っているので、特に注意して観察したはずである。その北斎がこのように描いているのだから、これが正しい。西洋のアーチェリーもこのような形になるということは、これが「本来の」弓の扱い方である。弓道しかやったことの無い人は、一度自分の弓でこっそりとこのようにして矢を放ってみると良い。狙い通りによく当たるのである。自分よりも前、すべてが視野に収まっているのでねらうことができる。しかし、「弓道」になると、馬手は耳よりも後ろに行き、視野から外れる。手を耳の後ろにまで引けば、ねらえるはずがない。弓道の形は、ねらうための形ではない。
弓道の場合、「動く的」はねらわない。しかも、的は腰よりも低い位置に「置いてある」。ということはどういうことか。あまりこういうところを弓道家は考えない。
「弓道は礼射である」
ということである。弓道の射形は、礼射の形であって、本来実際の弓の使い方ではない。非常に特殊な場合に限定される弓の使い方である。
どのように特殊かというと、「殿様の前で弓の力を100%出して的に中てる」ということである。
戦場で、狩猟で、弓道の射形で当てることは難しい。スピードが必要だからだ。弓道で「早気」というものがある。会に入ってすぐに離してしまう「病気」である。戦場や狩猟、つまり実戦において、矢を放つタイミングは相手の動きにもよってくる。弓道の場合は完全に自己都合である。だから早く矢を放ってしまうことが病気になるが、実戦においては早いか遅いかは問題ではなく、相手に当たるタイミングで放ったか、が問題である。
松波佐平弓具店のHPには東大寺通し矢絵巻があるが、そこの記載に
>一昼夜で一万本以上射るには、一分間に十~十二射射る事になる為に一本の矢が的に当たる頃には、次の矢が弦を離れており、三本目の矢が弦にかかっているという速射だったことがわかります。
とあるので、「会での充実」などしている暇はないのである。これが天保年間のことであるので、江戸時代の通常の弓といえば、北斎の描いたような射方が通常であったといえる。
弓道のような「礼射」は儀式的なものであって、実戦性のないものであると理解したい。
さて、では「礼射」とはなにかというと、弓の力を100%出して中てること、である。では、弓の力を100%出すにはどうするか、ということである。答えは子供でも理解できる。「弓を目一杯ひくこと」である。自分に押し開くことの出来る最大限開ききれば、それが弓の100%である。機械で押し開くわけではないので、弓と射手の複合の100%である。100%押し開いたときにどうなるか、というと、射法八節の会の状態になる。会の状態に「する」のではなく、会の状態に「なる」のである。
馬手のひじと、背骨、押し手の角見のラインが最大に伸びるようにする。そのとき肩甲骨の下側が寄り、上側が開ききることで肩の幅が数センチ伸びる。また、それを利用して脇の下背中側の筋肉を利用して弓を左右に「押し広げる」ようにする。最大限開ききったとき、「馬手に力が入らない」状態になる。「弓手に力が入らない」状態にもなる。「重心が少し前のめり」にもなる。「ひかがみに力が入る」。そういう状態になる。勝手になる。その状態から、左右にさらに数センチ押し広げると「離れ」る。なので、会での伸びあいは矢尺の伸びあいで、詰めあいは肩甲骨の下側を最大限詰めること、といったところである。その状態から、弓の力をさらに引き出すために、数センチ「押し広げる」つもりで開くと離れになる。
なぜ馬手や弓手に力が入らないかというと、背中側で最大限伸びるようにすると、馬手に力が入っていれば、馬手の手首によって腕のスジが引かれて、引きが数ミリ小さくなる。その数ミリを全力で伸ばそうとすれば、手首に力を入れていられない。全力で一箇所に集中すると、余分な場所に力を入れられないのが人である。このようにして上半身の弓手馬手の間隔を、肉体で確保できる最大量とり、さらにそこから伸びようとするとどうなるかというと、ひかがみに力が入り、足の裏で踏ん張ることになる。踏ん張る為には、足の開きの角度は大体60度である。
会の状態を基準として逆算で出したのが八節である。
最大限引ききるとどうなるかというと、足で踏ん張りながら、目一杯ピンと全身張っている状態になる。これは紙や布がぴんと張られている状態と同じで、一つの面を構成する。面は足踏みを基準とする。足踏みのラインで面を構成しているので、的までまっすぐになる。これが全力で引いていないと、からだにゆるみが生じて的をねらわなければいけなくなる。張っていればまっすぐなのでねらう必要が無い。これが「的が見えなくても中てられる」弓道独特の礼射である。
なので、実戦向きでは全く無いので、武術家はアーチェリーをやったほうがいいです。
と、書いたところで、以下のページを見つけた。ナイハンチを調べていたら出てきました。
清朝における弓の練習と、本部のナイハンチの型の写真。肩の後ろまで引いているけれど、ひじと矢がまっすぐ。ひじと矢がまっすぐであればここまで引いてもねらえる。試しにやってみたが、実によくねらえる。