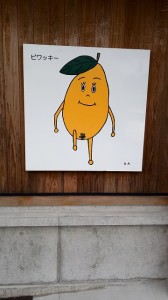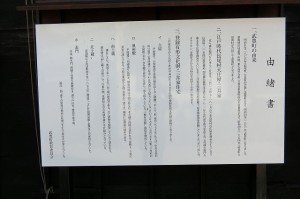スピリチュアル について
いろいろと考えていたのだけれども、中村元「ブッダ伝」を読んでいたら、
「スピリチュアルは、ポルノだな」
と思ってしまった。
シャカを語るにあたって、魂の浄化とか、魂の進む道とか、魂の目的とか、魂の導きとか、魂の繋がりだとか、まぁソウルメイトだとか、インチキじゃねぇか。
「神界と人間界と悪魔界とナントカ界と、縁を切って一人になれ」
ってシャカは言っているのであって、神の導きなんてものはウンコ以下である。
そういうウンコ以下の神の導きだのなんだのに興奮しているのは、ポルノ以外の何であろうか。
そもそも魂の輪廻転生をやめようね、って言っているのに「神界に転生するために魂を浄化しましょう」って何言ってるんだこいつ、ってことで、悟りを開けばつまりは魂は消えてなくなり、簡単に言えば「死んだらおしまい」になるのである。「死んだらおしまい」って当たり前だろ、ってことなんだけれども、そういうことである。
それでは魂ポルノにならないので、魂がなくなって困るスピリチュアリストは魂がなくならないようにがんばるのであるけれども、そうするといつまで経っても輪廻転生から抜け出せないのである。
「魂ポルノ」とは、良い言葉を思いついてしまった。
まぁ、ポルノだから、そういうもので自慰行為にふけるのは個人の自由なのでいいんじゃないでしょうか。
私はてっきり自慰行為集団だと知らずに真面目に悟りの道について問答してしまったので、彼らの自慰行為を中断せしめてしまったので、そこから追放されたのでした。いやぁ、ようやく理解できた。